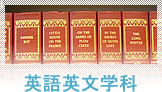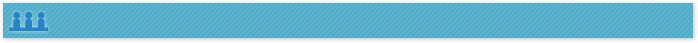 石木 利明 (いしき としあき)
石木 利明 (いしき としあき)
プロフィール
 文学に求めるのは、明快性や<癒し>というより、人間の心理や生のあり方の不安定さと曖昧性。その意味でアメリカ19世紀の作家たち、特にHawthorneとJamesに惹かれて研究しています。もう一つの関心は、デジタル・メディアが私たちの文化(例えば読みの対象としてのテクストやそれを読む行為)をどのように変えつつあるのかという問題。メディア論と文学批評理論とが交差する領域に関心をもっています。
文学に求めるのは、明快性や<癒し>というより、人間の心理や生のあり方の不安定さと曖昧性。その意味でアメリカ19世紀の作家たち、特にHawthorneとJamesに惹かれて研究しています。もう一つの関心は、デジタル・メディアが私たちの文化(例えば読みの対象としてのテクストやそれを読む行為)をどのように変えつつあるのかという問題。メディア論と文学批評理論とが交差する領域に関心をもっています。
主な著書・論文
- “Narrativity and Unreadability: Reading Henry James’s The Sacred Fount” 『駒澤大学苫小牧短期大学紀要』第19号、1987年。
- 「読むことの欲望を読む― “The Figure in the Carpet” と読者」『上智英語文学研究』第14号、1989年。
- 「英米文学研究のためのインターネット」『英語青年』第142巻 第10号、1997年。
- 「ハイパーテクストとポストモダニズム」『大妻女子大学紀要』第36号、2004年。
- 「原文の力―Anne of Green Gables ( 『赤毛のアン』)冒頭に学ぶ」『大妻レヴュー』第49号、2016年。
- S・R・バウン著『貿易商人王列伝ー会社が世界を支配した時代:1600~1900年―』(共訳)悠書館、2018年。
- 「”The Star-Spangled Banner”―注釈と翻訳」『大妻女子大学紀要』第53号、2021年。
- 「翻訳 シャーロット・パーキンズ・ギルマン『黄色い壁紙』」『大妻女子大学紀要』第54号、2022年。
- 「シャーロット・パーキンズ・ギルマン『黄色い壁紙』の謎解読のために」『大妻レヴュー』第55号、2022年。
担当科目
- 基礎セミナー1、2
- 英語ⅠA、B
- 米文学(近代)
- 英文講読(発展)1、2
- セミナー1、2、3、4
- 卒業論文
ゼミの紹介
教員から
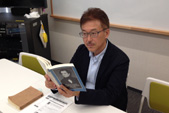 心に潜む深い闇。その淵に淀む澱。そういう、できることならば見過したい人間精神のネガティヴな部分を、文学はことさらにあぶり出そう、さらけ出そう、えぐり出そうとします。特にアメリカの文学は、人間の心の見えにくい部分に蠢(うごめ)く暗い衝動を表現することに取り憑かれた文学です。心の内にある得体のしれないもの、名状し難いものに戦(おのの)く経験を与えることこそ文学に課された使命であると言うかのようです。僕のセミナーでは、いつもそういう色の濃い作品を取り上げています。読んだ後、心が温かくなる話ももちろんなくてはなりません。しかし、僕にとって本当に面白い話とは、震える心に捉えられるものばかりなのです。
心に潜む深い闇。その淵に淀む澱。そういう、できることならば見過したい人間精神のネガティヴな部分を、文学はことさらにあぶり出そう、さらけ出そう、えぐり出そうとします。特にアメリカの文学は、人間の心の見えにくい部分に蠢(うごめ)く暗い衝動を表現することに取り憑かれた文学です。心の内にある得体のしれないもの、名状し難いものに戦(おのの)く経験を与えることこそ文学に課された使命であると言うかのようです。僕のセミナーでは、いつもそういう色の濃い作品を取り上げています。読んだ後、心が温かくなる話ももちろんなくてはなりません。しかし、僕にとって本当に面白い話とは、震える心に捉えられるものばかりなのです。
学生から
私たちのゼミでは、アメリカの恐怖小説を研究対象としていますが、おかしなことに、授業中笑いが絶えません。 クラスと学年を超えた仲間、他の授業でよりも身近に感じる先生。テクストだけでなく、そこからさまざまな話題に発展します。先生が米国滞在で得た生きた英語を学べるのも魅力です。ゼミ合宿も楽しい。いつもの仲間と新鮮な環境で勉強するワクワク感。勉強以外の楽しみもたくさんあります。もう一度ゼミ選択があっても、私は間違いなくこのゼミを選びます。



過去の卒論タイトル
- ヘンリー・ジェイムズ『ねじの回転』における女家庭教師の妄想的「洞察」
- ナサニエル・ホーソーン『緋文字』におけるジェンダー観
- 死と自立―ケイト・ショパン『目覚め』の研究
- 闇に囚われた女たち―「黄色い壁紙」における女・狂気・社会
- 抑圧と解放―スティーヴン・キング『ミザリー』へのフェミニスト的アプローチ