天野 みどり
専門分野
日本語学
オフィスアワー
木曜3限 E964A
井原 あや
専門分野
日本近・現代文学 ジェンダー論 国語科教育
オフィスアワー
木曜3限 E968A
神林 尚子
専門分野
日本近世文学
オフィスアワー
木曜3限 E965E
木戸 雄一
専門分野
日本近・現代文学 書誌学(近代)
オフィスアワー
木曜3限 E965B
君嶋 亜紀
専門分野
日本中世文学(特に和歌文学) 国語科教育
オフィスアワー
木曜3限 E955A
金ヨンロン
専門分野
日本近・現代文学 ポストコロニアル批評
オフィスアワー
木曜3限 E956B
久保 堅一
専門分野
日本中古文学
オフィスアワー
木曜3限 E969A
倉住 薫
専門分野
日本上代文学
オフィスアワー
木曜3限 E968B
小井土 守敏
専門分野
日本中世文学
オフィスアワー
木曜3限 E955B
桜井 宏徳
専門分野
日本中古文学
オフィスアワー
木曜3限 E957B
塩野 加織
専門分野
日本近・現代文学
オフィスアワー
木曜3限 E958B
内藤 千珠子
専門分野
日本近・現代文学 ジェンダー論
オフィスアワー
木曜3限 E958A
増野 弘幸
専門分野
中国古典詩
オフィスアワー
木曜3限 E966A
中尾 桂子
専門分野
日本語教育 応用日本語学
オフィスアワー
木曜3限 E966B
中山 愛理
専門分野
図書館情報学
オフィスアワー
木曜3限 E964B

天野 みどり AMANO Midori
日本語学が専門分野です。世界の言語は6000種類とも7000種類とも言われていますが、その中の1つである日本語を観察し、どのようなしくみによって複雑な意味を生み出したり解釈したりすることが可能となっているのかを明らかにしようとしています。その際、日本語だけに視野を狭めず他言語と比べることも重視し、人間言語の普遍性と日本語の個別性の問題も意識するよう心がけています。身近な現代日本語が主たる研究対象ですが、授業では様々な時代の文献資料を用いて、日本語の歴史を理解することもおこなっています。
教員から
言語学は「ことば」そのものを観察し、そこに潜む規則性やしくみを明らかにしていく学問です。学生の皆さんは、日常会話であれ小説のことばであれ、私たちが生きていく上で切り離すことのできない具体的なことばそのものを観察し、どのような意味がどのようにして生み出され理解されるかを考えていくことになります。ことばは流動的な社会・文化、人間の思考・心と関わり、現代語といえども柔軟な変化・変容を含んで常に揺れ動いているものです。さらに昔のことばを観察すれば、言語のダイナミックな部分、そしてその反対に決して変わらない普遍的な部分があることを発見することもできるでしょう。
ことばのしくみは人間がコミュニケーションをするために共同で創りあげてきたものです。ことばの研究により、現代を生きる皆さんのコミュニケーション活動に資する知見を得るだけでなく、そのようなしくみを創りだした人間とはどのようなものなのかということ、つまり皆さん自身を深く理解することにもつながっていくと思います。
学生から
過去の卒論タイトル

井原 あや IHARA Aya
近・現代の小説や雑誌(文芸雑誌・女性雑誌など)を、フェミニズムやジェンダーの視点を用いて研究しています。たとえば文芸雑誌では、投稿欄や読者欄等を分析し、作家・投稿者・読者と〈文学〉の関係を考察しました。また、女性雑誌では発表された小説と誌面の響き合いを確認する一方で〈ズレ〉にも注目し、社会や誌面が要請する理想と読者の現実を検討しています。教職科目も担当しています。
教員から
このゼミでは、近・現代の小説に描き出される社会と文学の繋がりや、文学が社会に投げかけたものについて、ゼミの皆さんが様々な視点を通して検討しています。
ゼミのよいところは2年間時間をかけて〈考えること〉〈書くこと〉に向き合える点です。テーマは違っても、3年生は4年生の発表や取り組み、たとえば調査の仕方や発表資料の作り方、目的の立て方、論の進め方などから卒論とはどういうものか段々と理解していきます。また、4年生は、3年生の発表にアドバイスをしながら自分の論文執筆に向って準備を進めます。
ゼミの時間は、皆さんの興味・関心、そして問題意識を確認しながら助言をしています。ゼミという〈場〉は、3年生と4年生、そして教員が互いに意見を出し合い、〈考えること〉〈書くこと〉に向き合う〈場〉です。こうした大切な〈場〉を皆さんと一緒に楽しみながら育んでいきたいと思います。
学生から
私たち井原ゼミでは、吉屋信子や太宰治、湊かなえといった近現代作家や『少女の友』などの雑誌を対象として卒業論文の制作やそれに向けた研究を行っています。
ゼミ内での発表の中で、質疑応答や、助言などを学生同士で行うことで、新たな視点が生まれたり、行き詰った時のヒントを得たりすることもあります。比較的人数が多いゼミなので、様々な意見交換ができてとても良い刺激になります。実際に、「自分に卒業論文が書けるのか」という不安を抱いていた私でも、上級生からの助言や同級生からの質問を通して、「今自分が研究したいことは何か」「どのように研究を進めて行けば良いのか」を理解し、卒業論文に向けて、日々研究に励むことが出来ています。また、井原先生はテーマ決めの段階から沢山相談に乗ってくださり、一人一人に対してしっかりと向き合ってくれるので、私たちも楽しく、そして安心して個々の研究に取り組めています!
過去の卒論タイトル

神林 尚子 KAMBAYASHI Naoko
近世(江戸時代)の文学、特に江戸の地で出版された絵入り小説(草双紙)が専門です。個人的な研究テーマとしては、一つの題材が複数のジャンルにわたってどのように脚色されて展開していくか、具体的な作品に即して考察しています。
近世には、小説や演劇、落語などの話芸なども含め、ジャンルを超えて一つの題材が扱われる例が多くみられます。いわばメディアミックスが盛んに行われていた状況を踏まえ、ジャンルを超えて題材の展開を辿ることを目指しています。
扱う時代としては、江戸時代の後期から明治の初期にかけて、近世から近代への過渡期を中心的な対象としています。従来の研究の区分では、近世(古典)と近代を分けて論じられることが一般的になっていましたが、明治初期の文学や演劇には、近世との連続性も多く見出されます。幕府の瓦解という政治的な転換期を経て、書物・文学や芸能の世界では何が継承され、何が変化していったか、という問題にも取り組みたいと考えています。
教員から
近世文学(明治初期の文学を含む)を研究対象として卒論を書く人たちのゼミです。井原西鶴の浮世草子や、曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』などの長編読本、鶴屋南北の歌舞伎など、時代もジャンルも様々な関心を持つゼミ生の方々が集まっています。
卒論ゼミでは、3年次から2年間にわたり、作品を丁寧に読み解くための訓練を積み重ねます。それぞれの興味や関心に応じて、まずは近世の様々な作品に触れ、卒論で取り上げたい作品や作者を探します。続いては、作品を本当に「読む」ために何をすれば良いか、注釈の付け方、文献の探し方や調べ方などの基本的な方法を身につけます。そして、最後には各自の関心に即したテーマを設定して、卒業論文としてまとめ上げることになります。
作品を的確に読み解くためには、まずは何が分からないのか、何をどう調べればよいか、ということを探るのが出発点になります。きちんと作品に向き合い、分からないことを調べて明らかにしていく作業は、大変なこともありますが、大きな達成感と知的な喜びをもたらしてくれます。その探求の道のりを、ゼミ全体で共有していきたいと願っています。
各回のゼミは、受講生がそれぞれの関心に基づいて、今考えたいことや調べていることの報告、あるいは現状で困っていることなどをまとめて発表し、それに対して質問や意見を出し合う形で進めます。4年生は、卒論の仕上げに向けて、集中して自分の論を練り上げていく時期にあたります。また3年生は、4年生の発表を見て学び、議論に参加することを通じて、自身の関心を育てていってほしいと思います。

木戸 雄一 KIDO Yuichi
幕末期から明治期の小説・評論の研究をしています。最近は「啓蒙」をキイワードに、教化や伝達の技術として「改良」を加えられた言語が、どのように人々の言語活動・思考方法などを変えてきたのかについて関心を持っています。それと関連して、近代の出版史や書誌学の研究もしています。近代の新しいメディアの様式がどのように生まれ、どのように経験されたのかについて考えています。そのために歴史文書などを利用した読者研究にも取り組んでいます。
教員から
近現代文学の時代は一世紀ほどしかありません。しかしこの間に「文学」の意味するところは大きく変わりました。小説の多くはかつて「文学」ではありませんでしたが、現在では「文学」と見なされています。「文学」作品に出てくる言葉や登場人物の動作も、今とは異なる意味で受けとられていたかもしれません。そして新しいメディアが生まれるたびに、「文学」の形式は変化し続けています。あなたの好きなあの作品も、全く違う読み方をされていたかもしれないのです。
書かれた時代や場所、また異なる立場の読者を想像しながら「文学」作品を読むことは、親友の過去を知ったら知らない人のようだったという体験に似ています。最初はショックかもしれません。でも、やがてあなたはその作品をより深く理解したことに気がつくでしょう。
学生から
卒論では「小説の書き方マニュアルの比較」に取り組むつもりです。マニュアルと言いながら、本・著者により内容が大きく違うのはなぜか、を考えることで、文学・小説の本質を少しでも見極めたいという思いからです。
ことばの表現から、時代から、作者から……、さまざまな視点から作品を読む面白さを私は大学で学びました。また、サークル活動で大学・学部を超え多くの人と接することで、同じ作品を読んでも一人ひとり感じ方が違うことを知りました。答えが一つに限らないのが文学研究の魅力。だからこそどこまで深められるか、文学と真剣に向き合ってみたい。今はそう思っています。
過去の卒論タイトル

君嶋 亜紀 KIMISHIMA Aki
教職科目も担当していますが、専門分野は中世の和歌文学です。新古今時代と南北朝期を中心に、和歌の表現や歌集の構想について研究しています。中世は武士が台頭し、戦乱や政争が相次ぎ、京都を中心にした古代の貴族社会が変質していった日本史上の転換期です。けれど王朝貴族社会で育まれた和歌は、そんな中世にも生き残り、担い手を増やしました。では、中世の人々は和歌に何を託し、何を表現したのか。和歌という詩的世界の表現方法を分析するとともに、和歌を通して中世の人々の「古」への憧憬や、伝統の継承と変容、時代・社会と表現との関わりについて考えています。
教員から
現代人が800年も前の中世の文学を読む意味はどこにあるのでしょうか。
社会の仕組みや価値観が揺れ動いた転換期の中世には、クセのある面白い人間が輩出しています。意志的で行動的な帝王・後鳥羽院や後醍醐天皇、王朝を憧憬し美意識を磨いた藤原俊成・定家の父子、旅に生き花月を愛した西行、新興都市鎌倉の武家歌人源実朝、そして式子内親王、建礼門院右京大夫、阿仏尼など、激動の世にあって自らの意志で作品を残した女性たち…。それぞれに魅力的ですから、ゼミ生たちの研究対象もバラバラです。でもだからこそ、互いの発表を聴き、異なる視点を知り、刺激を受けられる場になると期待しています。
ある時代状況や社会環境の中で生きた人間が残した古典を読むと、現代との共通性と異質性を発見するでしょう。それは自身を取り巻く現代社会という枠組を相対化する視点を得る営みでもある、と思います。みなさんとともに中世の作品を読み、古人に出会い、その表現意図を分析しながら、現代を生きるための知性も磨いていきたいと思っています。
学生から
「中世ってどんな文学があるの?」
と聞かれることが結構ありますが、様々なジャンルの文学が花開いた時代です。
和歌は勿論の事、軍記、説話、日記・随筆・・・・・・またその作者自身も個性豊かだったりします。
そんな中、君嶋ゼミでは各々が自分の好きなテーマ、作品で研究しています!扱っている作品は皆違えど、それぞれの研究テーマを尊重し、切磋琢磨して研究を進めています。
「そんな事情があってこの作品は生まれたんだね!」
「実はこんな意味があったんだ!」
「じゃあこれは?」
「こんなこと調べてみたら面白いんじゃない?」
皆仲良く、楽しく、卒業論文を進めています!
合宿では、先生とも和気藹々で、中世を巡る旅(昨年は伊勢)へ行っています。行き先は私たち学生が決めているので固定されていません。
ゼミでは新しい発見と驚きがいっぱいです!さて、今日はどんな発見があるでしょうか?
過去の卒論タイトル

金ヨンロン KIM Younglong
日本近現代文学と歴史の関係について研究しています。特に、戦争、言論統制、震災、パンデミックなど、文学の表現や読みに大きく影響を及ぼすような状況に関心をもっています。これまでの授業では、戦争文学(近代から現代まで)、戦後文学、震災後文学、法と文学、病と文学など、様々なテーマを扱ってきました。今後、比較文学や世界文学の方法について勉強し、授業でも活かしていきたいと思います。
教員から
ゼミ生が選ぶ作家や作品、時代、テーマは様々ですが、個々の作品と真摯に向き合う態度には共通しているところがあります。
卒論ゼミの進め方を簡単に説明しましょう。卒論のテクストが一旦決まると、ゼミの皆がテクストを丁寧に読み、細部について話し合います。一人で読んでいた時には気づかなかったことを、他の学生に教えてもらいます。たまには、テクストの読みをめぐって、異なる意見をぶつけ合うこともあります。テクストとの向き合い方は、他者とのかかわり方でもありますので、当然起こることです。こうした議論を通して自分の問題意識を明確にし、表現を見つける過程を経て、卒論を完成していきます。このプロセスを思い切り楽しみましょう。
学生から

久保 堅一 KUBO Kenichi
『竹取物語』や『源氏物語』を中心に、主に平安時代の物語文学を研究しています。作品のことばや表現を分析し、丁寧に読解することを試みながら、同時に、作品どうしの繋がりや、漢詩文・漢訳仏典の受容について明らかにすることも目指しています。物語文学や仮名文学はいかなる背景や基盤によって創造されたのか、そして、どのような主題が継承されていったのか、といった問題を考察することが近年の課題です。
教員から
『源氏物語』『落窪物語』『枕草子』など、平安時代の文学を卒業論文の対象とする学生が学ぶゼミです。ゼミ発表や討論をとおして研究の方法を学びながら、作品を丁寧に読む姿勢を身につけることを基本としています。
平安文学は〝みやび〟〝華麗〟といったイメージで捉えられがちですが、実はその内実は多様で、どれもこれも読み応えのある作品ばかりです。何しろ約千年も前の文学なのですから、解明されていないことも多く、容易に結論が出ないこともしばしばです。でも、だからこそ研究しがいがあります。ことばや表現の分布、本文の揺れ、史実との交渉、漢籍・仏典の受容など、様々なアプローチを試みながら真摯に作品と向き合えば、必ずや時を超えてその作品の魅力を感じられる、充実した時間が訪れます。ゼミ生たちには、授業をとおして基礎を学びながら、自ら積極的に作品を読み込み、自分のことばで平安文学ならではの魅力について語れるようになることを期待しています。

倉住 薫 KURAZUMI Kaoru
柿本人麻呂の作品を中心に万葉集の表現を研究しています。 研究は、本文校訂・訓読の確定といったある意味地味な作業から始まりますが、ひとつひとつの〈ことば〉に込められた〈こころ〉を読みとっていくことに興味がつきません。相聞とは、挽歌とは、季節の歌を詠む〈こころ〉とは……
また、万葉集と同時代の古事記・日本書紀・風土記なども、当時の社会制度や状況そして物語を伝えてくれる重要な文学作品であると考え研究しています。歴史書や地誌として捉えられがちですが、とても魅力的な神様や人々が活躍する物語も多く存在しています。
さまざまな人の〈こころ〉を揺さぶる人麻呂の歌や万葉集の魅力に迫っていきたいと思っています。
教員から
上代文学のゼミでは、万葉集や古事記・日本書紀・風土記など、日本の最も古い文学作品を研究しています。
現代と1300年以上隔たった上代の世界は、まだまだ分からないことだらけです。例えば、古事記の語り出しである「天地初発」は、どのように訓読するのか、日本の創成はどのように語られているのか……いまもまだ決着がついていません。
こう書くとなにやら難しいばかりのわからないことだらけのように思われるかも知れませんが、古事記や日本書紀には、大げんかをしてしまう神さまたちや、浮気をして奥さんに嫉妬されてばかりの天皇など、人間味あふれる物語がたくさんあります。古典の中の女性と言えば、待つばかりで受け身と思われがちですが、万葉集では、男たちに腹をたてた女性が大胆な歌を詠んだりもしています。
現代や古典の常識が通用しないことがあるのも、上代文学の魅力です。作品と向き合うということは、自分が培ってきた了見や価値観が問われ、覆されることでもあります。用例分析や当時の状況を理解しながら、自由な発想で作品を解釈していって欲しいと思っています。
学生から
私達、倉住ゼミはゼミの時間に一人ひとり必ず発言する、参加型のスタイルです。発表の司会も学生が務めます。聞いているだけでは退屈になってしまう時間も、「何がわからないか」「自分はどう感じるか」という考える力を養う時間になります。発表者も様々な質問や意見を参考に、より研究内容を掘り下げる機会になります。
研究対象は『万葉集』『古事記』が多いです。倉住先生は上代文学に広く精通しておられ、参考になる論文を紹介して頂いたり、わからないことを丁寧に教えてくださいます。
また、新歓とゼミ合宿の企画、幹事を四年生が務め、追いコンを三年生が務めます。「自分たちで全部やる」ことは簡単ではありませんが、必ず自分たちにとってプラスになります。
ここ数年でゼミ生が増え、和気あいあいとゼミ活動を行っています。
過去の卒論タイトル

小井土 守敏 KOIDO Moritoshi
中世の軍記文学を中心に研究をしています。『平家物語』や『曾我物語』といった作品の生成過程と本文の変化・流伝について、文献学・書誌学的な見地からの実態解明に関心を持っています。また、軍記文学作品を読み込んでいくことで、中世という激動の時代をたくましく生き抜いた人々の生死観や美意識についても考えていきます。
軍記文学に深く関連する説話文学、また謡曲などにも研究対象を広げています。
教員から
武士階級の台頭と貴族の没落、たび重なる戦乱と末法思想――。中世という時代 はそこに生きた人々に、価値観の大きな転換を迫りました。『平家物語』を引くまでもなく、目の前で大切な人や物が損なわれていく現実に、人々は「無常」なるものを実感したことでしょう。しかし彼等は、下を向いてばかりではありませんでした。無常さえも肯定的に受け入れ、つかの間の平和を楽しみ、多様な文芸を創り出しました。それは中世人(ちゅうせいびと)のあふれんばかりのエネルギーです。
文学史上に見る“ジャンル”の多くが、この時代に生まれました。その多様なジャンルの多様な作品に込められた新しい価値観は、現在に生きる我々にも受け継がれています。そうした、昔と今の共通点を発見していくことは、深い人間理解にも繋がっていくはずです。
学生から
卒論ではひとつの作品を選び、先行論文も参考にしながら自分なりの読み方や考察を深めていきます。
私は『平家物語』を熊野との関わりを軸に読み解こうと思っています。きっかけは大学1年の夏休みに熊野古道を歩いたことです。自分がその場に立ったことで、熊野信仰の存在を身近に感じられるようになりました。
その後、あらためて『平家物語』を読むと、淡々と書かれている文章の中に作者の思いが感じられる箇所を見つけたり、当時の死生観や信仰心を推し量れる部分があったりと、気づかなかったものが見えてきて研究がどんどん楽しく なったのです。卒論では自分が感じた作品のおもしろさを、うまく表現したいです。
過去の卒論タイトル

桜井 宏徳 SAKURAI Hironori
平安時代の仮名文学(物語・日記・和歌など)と、平安時代から江戸時代までの歴史物語を主に研究しています。現在の研究の中心は『栄花物語』ですが、最近は江戸時代の歴史物語『月のゆくへ』『池の藻屑』の注釈にも取り組んでいます。
授業では『栄花物語』のほか、『古今和歌集』『源氏物語』『堤中納言物語』『大鏡』や紀貫之・和泉式部の和歌など、平安時代のさまざまな作品を扱っています。
教員から
平安時代の文学に関心を持つ皆さんとともに学びながら、卒業論文を書くための指導と助言を行っています。平安文学に関わるものであれば、作品の選択やテーマの設定は自由ですので、ゼミ生の卒業論文もバラエティ豊かで、たとえば、『源氏物語』の作中人物と色彩との関係を紫の上の視点から分析するもの、『古今集』を代表する歌人の一人・凡河内躬恒の和歌表現の特色について論じるもの、『和泉式部日記』における「女」と「宮」の関係を贈答歌から読み解くものなどがあります。
ゼミ発表や卒業論文の執筆に際しては、作品そのものをことばや表現に即して丁寧に読み込むことはもちろん、先行研究をきちんと踏まえることを重視しています。と同時に、私自身の関心に即して皆さんを誘導してしまわないように、つまり、皆さん自身のアイデアをできる限り活かすように、と心がけています。皆さんの自由で柔軟な発想から、私たち教員を驚かせるようなユニークな論文が生まれることを期待しています。
学生から
私たち桜井ゼミでは、平安時代の日記文学や和歌などの作品を、様々なテーマで日々研究しています。私は『源氏物語』における色彩と人間関係を対象にしていますが、一見私にはあまり関係なさそうな研究をしている仲間もいます。しかしゼミ生の数だけ研究内容があり、その中から自分にはない新たな視点や知識を広げられるのを毎週楽しみにしています。
ゼミはそれぞれの中間報告に対し、先生や仲間から助言をもらうというスタイルです。桜井先生は広い心で丁寧に、私たちの意見を尊重しながらアドバイスして下さったり、色々な相談も聞いて下さいます。少人数でまったりとした、まさに平安時代のような雰囲気を感じ、楽しみながら研究をしています。
過去の卒論タイトル

塩野 加織 SHIONO Kaori
専門分野は日本の近現代文学です。井伏鱒二作品の研究から出発して、これまでに、戦時下の文学と日本語政策の関わりや、GHQ占領下の検閲出版制度、日本語のかなづかいやルビといった表記と文学表現の関わりについても研究してきました。近年では、翻訳研究にも関心を持っています。文学作品をとりまく文化的背景はもちろんのこと、社会的・経済的背景を踏まえながら、ことばの様々な働きを明らかにしたいと考えています。
教員から
卒業論文は、もちろん自分ひとりで書くものですが、執筆までの準備のプロセスには様々な人が関わっても良いと考えます。このゼミでは、学生同士がお互いのテーマや研究対象を知り、相互に意見を交わすことを積み重ねながら、2年間かけて卒業論文を準備していきます。また、3年生と4年生が相互に学び合い気軽に交流できるように、小グループに分かれて活動するワークショップの時間も設けています。研究テーマは様々で、明治期から現代に至るまでの小説・詩・童話のほか、映像作品や舞台脚本を扱う学生もいます。
ゼミの良さは、自分ひとりでは気づかなかった様々な見方や考え方に触れられることです。時にはあっと驚くような面白い視点に出会うことも少なくありません。こうしたライブ感のある知的刺激を体験できるのはゼミという空間ならではだと思いますので、その面白さを共有できたらと思っています。読んだり書いたりはもちろんのこと、自分の考えを話したり、他の人の意見を聴いたりする機会を大切にしながら卒業論文を育てていきましょう。

内藤 千珠子 NAITO Chizuko
近現代の小説を対象とし、ジェンダーとナショナリズムの関係をテーマに研究しています。物語のしくみを考えていくと、物語を成り立たせる差別の問題に出会わざるをえませんが、なぜ物語が差別の構造を含みもつのか、女性身体や植民地、帝国、境界の表象を通して考察してきました。
小説の言葉は、見えにくい物語の制度を、目に見える姿として描き出し、わたしたちの日常を縛るのとはちがった世界像を手渡してくれます。そうした文学の魅力と可能性について、考え続けていきたいです。
教員から
思考のスタイルをみつけること。このゼミでは、それぞれが自分のテーマをとおして「考える力」を身につけるために、発表者と聞き手との間で、深みのある議論が交わされています。自らの考えを言葉にして発表し、他者の声を聞き、拾い上げ、ときに葛藤しながら、自分を壊して学ぶ体験を積み重ね、自分らしい卒業論文を作り上げていく時間です。
3年生と4年生が批評的な意見をやりとりしあいながら、学年の隔たりなく、少しずつ親しくなっていけるように心がけています。
ゼミでの学びと交流をとおして、近現代の文学を読むことと、いま自分が生きて在ることの意味とをつなぐ言葉を手に入れてほしいと願っています。
学生から
過去の卒論タイトル

中山 愛理 NAKAYAMA Manari
アメリカ合衆国における公共図書館サービスの歴史や現状を中心に研究をしています。公共図書館におけるサービスをアウトリーチの視点から分析することで、図書館のもつ本質を明らかにすることに関心をもっています。また、図書館の物理的な空間から図書館サービスを捉えることで、そこを利用する図書館利用者がどのように認識され、位置づけられてきたのかを分析することにも関心をもっています。最近は、アメリカ合衆国にとどまらず、研究対象をさまざまな国に広げることで、比較研究も進めています。
教員から
メディア文化論の授業では、図書、マンガ、新聞、雑誌、ラジオ、映画、テレビ、インターネットをはじめとする多様なメディアの特徴と変遷について学んでいきます。各種メディアが誕生した背景に着目しつつ、メディアを通してどのような人が読み、人々の暮らしとその文化に影響を与えてきたのかについて分析・批判的に考察することを目指しています。この授業を通じて、みなさんが文学コンテンツ(作品)を伝えるメディアという存在について、理解を深めていくことを期待しています。
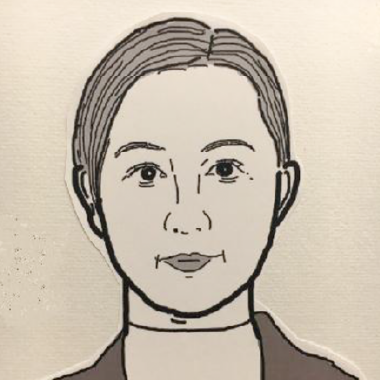
中尾 桂子 NAKAO Keiko
<研究の背景>
高等学校在学時のクラブ活動を通してヴェトナム難民の方々と出会い、日本語教師という職業を知りました。社会、国際、奉仕、言語を考えながら人のために働くことができるだろうと思って大学で副専攻の日本語教員養成課程を履修し、卒業後、日本語教師として働き始めました。日本語学校から、実践の場を広げ、小学校、中学校、公益財団、高等教育機関、国際交流協会といった様々な機関で、それぞれの目的のために日本語を学ぶ人々に、外国語としての日本語を教えることに勤しみました。
<研究活動に入った背景>
日本の公立小・中学校に転入した外国籍の児童・生徒に、日本語指導という名目で補習授業を担当しているとき、当時、成人日本語教育のベースとして捉えられていた日本語教育で言う「基本」とか「文型」に疑問を抱くようになりました。文型や文法項目を手掛かりにそれらの知識を積み上げて学ぶことが、年少者にどのくらいの意味があるのだろうかと思ったからです。そこで、働きながら通えそうな大学院に進学して、まず、語学教育用の「文型」というものが,本当に文の基本の型として子どもの言語習得の役に立つインデックスになるのだろうかという問いを立てて、手始めに、小学校の教科書を基本文型に当てはめること、また、基本文型で把握できる教科書の文章はどの程度かを調べました[1]。
[1]「小学校検定教科書の構文調査 -外国人児童の教科学習支援のための基礎研究-」小出記念日本語教育研究会『論文集』7, pp.41~55. 1999.
<大学院での研究>
基本文型を構造の型と考えて、正規表現という抽象化されたコンピュータ用のプロトコルを使って、大量の日本語を処理するという技術を応用し、計量的に小学校の検定教科書を文型で分類してみたのですが、当時、日本語教育で主流であった「文型」をベースに日本語を教える方法は、小学校の教科書を読むためには役に立たないだろうという結論に至りました。
ただ、正規表現を用いた方法は誤用も多いという欠点もありましたので、博士後期課程に進学し、そちらで、正規表現を使うのではなく、XMLというHTMLに似たプロトコルを用いて、言語を簡易データベース化するという方法で、それぞれの文章構造の枠の中でのパターン検索により、検定教科書を調べてみました[2]。しかし、やはり、談話構造に基づいて様々に位置づけられる日本語の書き言葉を、抽象化した「文型」で捉えることはできないだろうと思われました[3]。
[2]「日本語教育のための表現意図出現パターン調査における文書データベースとXMLの活用」(社)情報処理学会『人文科学とコンピュータシンポジウム論文集』情報処理学会シンポジウムシリーズVol.2000 No.17,
pp.177〜184.2000.
[3]「外国人児童用日本語基本語彙表選定における重要度決定尺度―残差IDFを利用した自動識別法の検討―」統計数理研究所共同研究リポート199『日英語の基本語抽出における統計手法の研究』pp.61-87.2007.
<現在>
はじめは現場に還元できる方法を考えるために工夫して研究していたのですが、徐々に、研究方法をいろいろ試したり比べたりすること自体に興味が移り、現在は、日本人のための実用的な言葉や文章の書き方や、教員養成についても考えるようになっています[4]
[5]。
[4]「品詞構成率に基づくテキスト分析の可能性―メール自己照会文,小説,作文,名大コーパスの比較から―」大妻女子大学『大妻女子大学紀要-文系-』第42号,pp101-128.2010.
[5]「主体性涵養のための学科連携にむけて−学生のパーソナリティ,学生の学習行動,教師の心象に基づく提案−」Uela&Jade 38-39(2022.3.8口頭発表)

増野 弘幸 MASUNO Hiroyuki
中国最古の詩集『詩経』を中心に研究をしています。研究テーマは、詩の表現と当時の習俗の関係について考えてゆくことです。古代においては重要な意味を持っていたと思われる鳥や、香草を始めとする植物、また、中国の都市には必ず設けられていた城壁と城門といったものの持つ意味について、『詩経』の詩を中心に漢代、六朝の詩あたりまでの詩を取り上げ、時代ごとの特徴や、影響、認識の変化について分析を試みています。
教員から
中国文学のゼミ生達は、古くは6000年前の仰韶文化にも形跡の見られる太陽と烏の神話の研究から、新しくは清の怪異譚集である『聊斎志異』の研究まで、非常に長い歴史の中でそれぞれにテーマを選んで卒論に取り組んでいます。
私自身は周の時代の『詩経』等、古い時代の文学が好きなのですが、学生達はその様なことには全く御構い無く哲学や歴史の分野にまで踏み入ってテーマを見つけて来ます。そもそも中国の学問には、文学や哲学といった明確な区分などありませんので、各人好き好きに興味を持って楽しく研究が出来ればそれで良いと思っています。文献の探し方や論の展開についてきちんと押さえてゆけばかなり深い所まで探求してゆけ、面白い論文が書けます。
後は各自の取り組みの度合いで完成度がかなり左右されてしまうので、この点、注意が必要です。
学生から
私たちは、悠久な歴史と広大な土地を持つ中国でつくられた多彩な文学作品について、時空間を超えて、当時の人々の言葉や心に耳を傾けた研究をしています。
ゼミは、朗らかで優しい先生に惹かれた生徒たちが集まっており、和気あいあいとした雰囲気で進行されます。ゼミ合宿では勉強だけでなく、ぜいぜい息を切らして筑波山に登ったり、一面に輝く綺麗な星空の下で花火をしたりと、楽しさ満点です。このゼミに入って悔いはなし
過去の卒論タイトル

