石川 千暁
専門分野
アフリカ系アメリカ文学、神秘主義
オフィスアワー
水曜昼休み E1064B
石木 利明
専門分野
19世紀米文学、批評理論
オフィスアワー
木曜3限 E1065B
伊東 武彦
専門分野
英語教育学、異文化間コミュニケーション
オフィスアワー
木曜3限 E1068B
江連 和章
専門分野
英語学、言語学
オフィスアワー
火曜4限 E1055B
大島 範子
専門分野
16-17世紀イギリスの詩と演劇
オフィスアワー
水曜4限 E1067A
新谷 敬人
専門分野
音声学、音韻論
オフィスアワー
水曜5限 E1064A
鈴木 紀子
専門分野
アメリカ文化・アメリカ研究
オフィスアワー
金曜3限 E1063B
田代 尚路
専門分野
英文学、19世紀英詩
オフィスアワー
木曜4限 E1056B
千田 誠二
専門分野
英語教育学、英語学習者論
オフィスアワー
金曜5限 E1058A
夏目 康子
専門分野
イギリス小説、英語圏児童文学
オフィスアワー
火曜日4限 E1061A
早川 友里子
専門分野
19世紀英文学
オフィスアワー
木曜3限 E1065A
村上 丘
専門分野
英語学、言語学
オフィスアワー
月曜2限 E1054B
森井 美保
専門分野
アメリカ文学
オフィスアワー
火曜2限 E1066A
Hywel EVANS
専門分野
理論言語学、計算言語学、社会文化理論、文化心理学
オフィスアワー
水曜日2限 E1057A
Ken IKEDA
専門分野
アメリカ文化、英語教授法
オフィスアワー
木曜2限 E1066B

石川 千暁 ISHIKAWA Chiaki
愛について、とりわけ自分を愛することについて研究しています。私の専門領域はアメリカ文学(とくにアフリカ系アメリカ文学)とジェンダー研究ですが、現在扱っているのは文学作品にとどまりません。希望と喜びを感じられるような教育がしたいと思い、ヨガや瞑想など、自分を良く知ってととのえる方法や思想についても理解を深めてきました。効果のある実践を積極的に授業に取り入れ、頭で<考える>だけでなく、心と体で<感じる>ことの大切さを伝えています。
教員から
The dream is the truth.– Zora Neale Hurston
共に学んで、内側から輝く、愛に溢れる女性になりませんか。石川ゼミでは、日本語や英語の文章、音楽や映像などのさまざまな教材を用いて、女性である自分を愛し、豊かに生きていくための基本を学びます。頭を使うばかりでなく、心と体とのつながりを取り戻すために、瞑想や呼吸法などの実践も行います。
文学作品を扱う場合、取り上げるのは、皆さんが共感でき、実際の悩みに対する答えが得られるような物語。発表やディスカッションを通して、作品の背景や登場人物の心情などを丁寧に読み解きます。ただ作品を理解して終わりにはせず、学んだことを取り入れて、自分自身の生活を改善していきます。最近では、黒人女性作家ゾラ・ニール・ハーストンの代表作を扱い、主人公のジェイニーが、どんなに苦しい時でも意地悪な人間にならず、困難を乗り越えて夢を叶えることができたのはなぜか、ということを学びました。
卒論指導では、卒業する時にどんな自分になっていたいかを話し合い、その夢にしたがって、扱う作品とテーマを決定します。何度も読み、よく考えて書いているうちに、憧れの女性像は次第に自分自身の姿になっていきます。
学生から
「自分は何のために生きてるんだろう?」って疑問に思ったり、将来を不安に思うことはありませんか。私は石川先生に出会って、色々な文章を読んで自分になかった考え方を得ていくうちに、毎日が豊かになり、幸せを感じられるようになりました。自分の中に眠っていた輝きを見つけることができたので、これからの人生がとても楽しみです!
このゼミは、私たちが忘れがちな、学ぶことの楽しさや言葉の大切さを思い出させてくれます。文学というと堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、石川ゼミはとても話しやすい雰囲気です。皆の発言を受け取ってくれるので、自分の考えや気持ちを話すのが苦手な人でも安心して話せると思います。私自身、発言するのは得意ではなかったのですが、ゼミを通して、先生から一方的に学ぶだけではなく、積極的に自分の意見を言うことができるようになりました。
過去の卒論タイトル
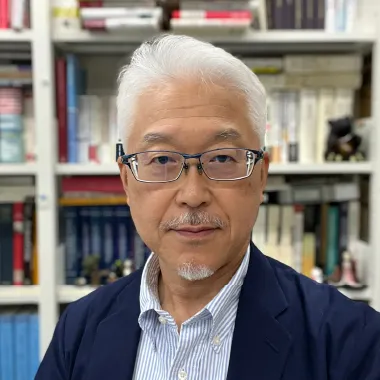
石木 利明 ISHIKI Toshiaki
文学に求めるのは、明快性や<癒し>というより、人間の心理や生のあり方の不安定さと曖昧性。その意味でアメリカ19世紀の作家たち、特にHawthorneとJamesに惹かれて研究しています。もう一つの関心は、デジタル・メディアが私たちの文化(例えば読みの対象としてのテクストやそれを読む行為)をどのように変えつつあるのかという問題。メディア論と文学批評理論とが交差する領域に関心をもっています。
[ E-mail ]ishiki@otsuma.ac.jp
教員から
心に潜む深い闇。その淵に淀む澱。そういう、できることならば見過したい人間精神のネガティヴな部分を、文学はことさらにあぶり出そう、さらけ出そう、えぐり出そうとします。特にアメリカの文学は、人間の心の見えにくい部分に蠢(うごめ)く暗い衝動を表現することに取り憑かれた文学です。心の内にある得体のしれないもの、名状し難いものに戦(おのの)く経験を与えることこそ文学に課された使命であると言うかのようです。僕のセミナーでは、いつもそういう色の濃い作品を取り上げています。読んだ後、心が温かくなる話ももちろんなくてはなりません。しかし、僕にとって本当に面白い話とは、震える心に捉えられるものばかりなのです。
学生から
私たちのゼミでは、アメリカの恐怖小説を研究対象としていますが、おかしなことに、授業中笑いが絶えません。 クラスと学年を超えた仲間、他の授業でよりも身近に感じる先生。テクストだけでなく、そこからさまざまな話題に発展します。先生が米国滞在で得た生きた英語を学べるのも魅力です。ゼミ合宿も楽しい。いつもの仲間と新鮮な環境で勉強するワクワク感。勉強以外の楽しみもたくさんあります。もう一度ゼミ選択があっても、私は間違いなくこのゼミを選びます。
過去の卒論タイトル

伊東 武彦 ITO Takehiko
英語教育学と異文化間コミュニケーションが専門です。
英語教育学では、1)教授法、2)カリキュラムデザイン、3)教材論、4)評価、5)教師論、6)外国語教育政策、7)異文化間コミュニケーションなどのテーマのもとに、英語教育のあり方を研究しています。これらの研究を基に、優れた英語教師を育てることに力をそそいでいます。
異文化間コミュニケーションでは、1)ターン・テーキング、2)ハイ・コンテクストとロー・コンテクスト、3)アサーティブ・コミュニケーションなどのテーマのもとに、異文化間コミュニケーション能力を向上させる方法を研究しています。
教員から
もし、あなたが “You look great in that dress!” (そのドレス、とても似合ってるね) とほめられたら、どう答えますか? 多くの日本人は、 “Oh, no … not really.” (そんなことないよ) と否定するでしょう。それが日本の文化では謙虚だとされます。しかし、英語の文化では “Thank you.” とお礼を言うのが一般的です。人をほめるのは、その人に好意的な気持ちを持っているからです。ほめたことを否定されると、好意も拒絶されたように感じられます。このような習慣を知らなければ、英語で適切にコミュニケーションすることはできません。
人々が国境を越えて異なる文化の人々と交流する機会が飛躍的に増えています。それにつれて、外国語学習・教育と、異文化間コミュニケーションの研究の重要性が世界的にますます認識されつつあります。外国語学習とは、単に単語や文法を習得することではなく、異なる文化の人々とのコミュニケーションを通して、人が新たなアイデンティティーと世界観を築く過程でもあります。この考えに立って、伊東ゼミでは「英語教育」「異文化間コミュニケーション」を中心テーマとします。発表と討議の場を多く持ち、学生が自分の意見を発表する力を高めることに力を入れています。
学生から
過去の卒論タイトル

江連 和章 EZURE Kazuaki
私の専門は、言語学の一分野である、英語学研究です。特に、英語の意味や語用(使用法)の領域に深く関心を寄せ、ここ最近は「(動詞や文によって)言語化されるデキゴト(事象)」はどのように構造化されるのか、また、実際にそれはどのように使用されるのか等について研究を重ねています。
英語という個別言語を、それだけに焦点を当てるのではなく、「人間のみが有する言語(「人間言語」)とはどのようなものか」というより広範な視点、文脈から、究明することが大切だと考えます。英語が私たちに示してくれる豊かな意味や文法、用法の世界の中でも、どの側面が人間言語共有の財産であり、どの側面が英語そのものの個性、つまり「英語らしさ」なのかについて明らかにすることを目標とします。
教員から
このゼミでは英語の意味と語用の世界に踏み込み、英語の形(音声、表現、文法)と意味のつながり、そして具体的場面での使用法に焦点をあてた学習と研究を行います。特に、英語の「発想(志向性)」という全体的視点から様々な事例を検証、分析することを意識し、日本語との比較も交えながら、「英語らしさ」とも呼べる英語の特異性(個性)について理解と考察を深めていきます。
具体的には、英語の意味論や語用論について学習を進めながら、学生それぞれの関心に応じたテーマを設定し、小説や映画、翻訳、新聞、広告等を題材に各自調査、研究を進めてもらいます。英語の「発想」という視点からの研究を主眼としますが、さらには、英語圏の文化や社会との関係も視野に入れると、考察の幅と深みが増すことでしょう。授業内での発表と全体での意見交換を重ねながら、学習と研究の集大成である卒業論文へと発展させます。
学生から
江連先生のゼミでは意味論、語用論の2つについて深く研究します。学生が自分の興味のあるテーマの文献を調べます。調べた文献を学生同士で発表して意見交換をしています。学年関係なく意見や質問を言い合えるゼミです。今まで知らなかった英語の仕組みを深く学ぶことができるのがこのゼミの特徴です。興味のある文献を調べているので、卒業論文のテーマの決定にもつながり意欲的に卒業論文に取り組めると思います。
過去の卒論タイトル

大島 範子 OSHIMA Noriko
17世紀のイギリスで書かれた詩と演劇を専門に扱っています。17世紀は、イングランド内戦(ピューリタン革命)と呼ばれる、イギリス史上前例のない事件が起こった世紀です。この、国王と議会が反目しあい、最終的に議会が国王を裁判にかけて処刑する、という非常にショッキングな事件は、しかし同時に、イギリスが絶対王政から立憲君主制へと移行する流れを作った、歴史上非常に重要な出来事でもあります。
私はそのような、前例がなく、したがって先を見通すことも出来ない不安定な状況で書かれた文学が、いかに恐ろしい体験と向きあうか、ということに関心を持っています。主にジョン・ミルトンや、アンドリュー・マーヴェル、ウィリアム・ダヴェナントなどを研究対象としています。
教員から
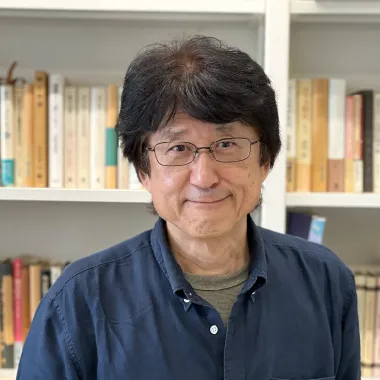
吉川 信 KIKKAWA Shin
「イングリッシュ・ノヴェル」の誕生は、この国の植民地拡大と軌を一にしているようですが、その「ノヴェル」を実験的に破壊してみせたのは、最古の植民地アイルランドに生まれた作家でした。ジェイムズ・ジョイスの方法と様々な「イングリッシュ・ノヴェル」との関係に興味があります。思えば『ガリヴァー旅行記』を書いたのはアイルランド生まれのスウィフトでしたし、帝国の黄昏を描いたのはポーランド生まれのコンラッドでした。最近の「イングリッシュ・ノヴェル」を牽引しているのが、日本生まれのカズオ・イシグロというのも、とても面白いことだと思います。
[ E-mail ]kikkawas[at]otsuma.ac.jp
教員から
何を語るにせよ、テキストを精読するところから始めたい、と思っています。そのため1回の授業は遅々たる進行具合で、思ったように読み終えられないことしばしばです。自分のほうが、1冊を何年もかけて精読させるような作家を読んできたせいで、「神は細部に宿る」と信じているのかもしれません。できるだけ多くの作家・作品に触れてもらいたいので、短篇を扱うことになりますが、他方では、長篇をざっくり要約してもらうような回があってもいいな、と思っています。フランスやロシアの大長篇(翻訳)を夢中で読み耽るなんてことは、時間のある学生時代の特権です。母語にせよ外国語にせよ、精読と速読(乱読?)の両輪駆動が理想でしょう。読んで、考えて、書く――この繰り返しに馴染んでくれば、難しい英文も楽しくなること必定です。
学生から
このゼミでは、イングランドやアイルランドの様々な短編小説を読みます。毎週の予習は欠かせませんが、分からない所は先生が分かりやすく説明して下さるので、何も心配は要りません。先生が一方的に授業を進めるのではなく、私達も参加して授業が進んでいくので、とても知識が深まります。ゼミの雰囲気もとても和やかで温かく、先生と学生の仲も良いので、毎週この時間が楽しみです。
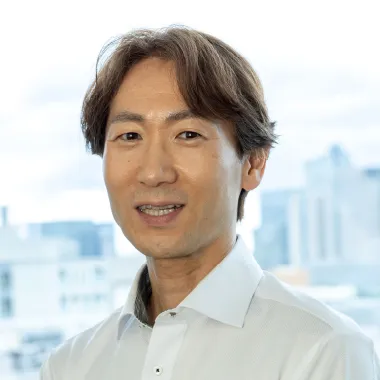
新谷 敬人 SHINYA Takahito
私の専門は音声学(phonetics)です。音声学は言語学の一分野で、ことばの音を研究します。音声の研究にもいろいろありますが、近年関心を持っている問題は英語の発音教育です。これを二つの側面から研究しています。
一つの側面は、私たち日本語ネイティブスピーカーが英語の発音を習得しようとする時、何に困難を覚えるのか、何を優先的に学習すべきか、またどのような訓練方法がより効果的なのかというものです。英語は一義的にはコミュニケーションのためのツールですから、相手に伝わらないと意味がありません。一方で私たちの英語には訛りがあるのが当たり前で、これを完全に取り除くのは極めて困難であるし、またその必要もありません。理解される英語のためには発音のどの側面が重要で、どこをどう直せば通じるのかを考えています。
私の研究のもう一つの側面は、言語態度の問題です。言語を使う人は必ず何らかの「訛り(accent)」を話します。英語も例外ではなく、われわれ日本人は多くの場合アメリカ英語を主とする訛りを「お手本」として学習します。その結果、アメリカ英語もしくはアメリカ英語に近い英語だけをまともな英語であるとみなしがちになり、日本語訛り英語を含めた、他の訛りに対して否定的な態度を取りがちになります。しかし現代世界では英語の話してはむしろノンネイティブスピーカーの方が多くなっています。現実世界で英語を使う場合、むしろ非アメリカ英語的で、ノンネイティブスピーカー訛りの入った様々な種類の英語の方が聞く機会が多いでしょう。この、ある種「差別的な」言語態度を変えていく方法について考えています。
[ E-mail ]tshinya@otsuma.ac.jp
教員から
新谷ゼミは一言で言えば「発音のゼミ」です。私たち日本語ネイティブスピーカーが英語を使う場面の多くは(当たり前ですが)相手は外国の人たちです。そして、その相手は英語のネイティブスピーカーではないことも少なくありません。この点は見逃されがちです。私たちも相手も自分の母語ではない英語を外国語として使うのです。現代ではこの状況が世界的に普通になりつつあります。外国語では理解度が下がりますから、英語のネイティブスピーカーになら通じていた発音が英語を外国語として使う話者には通じないということが起こります。新谷ゼミではこの状況に注目し、相手が英語ネイティブとは限らない状況で英語発音のどこが理解にとってもっとも重要なのか、様々な言語を母語にする人たちの様々な英語はそれぞれどのような特徴があるのか、日本語ネイティブスピーカーの英語は日本人以外の人にはどれくらい理解されまたどのように感じられるのかなど、英語の発音を「国際共通語」という観点から考察します。同時に自身の発音を向上させることを目的として発音の練習も行っています。
学生から
私たちのゼミでは、英語学の音声学について研究しています。音声学では口の中のどの部分をどう使って発音しているのかを学んだり、コンピューターを使って音声を可視化して音の伝わりを学んだり、私たちが英語の音をどう聞くかを学んだりします。またいろいろな英語の方言の発音の特徴についても扱います。発音と文章を読む時のリズムを練習する時間があるのですが、アメリカに長く住んでいた新谷先生から直々に個人指導していただけます。なかなか難しいのですが、とても実用的でためになります。
このゼミは英語の発音について学ぶことができるので、発音を良くすることができます。先生の教え方がとても丁寧で優しいので、授業が苦手な私でも意欲的に取り組めます。
先生は優しくて、とても丁寧に指導してくれます。英語を話したり、聞いたりすることが好きな人に向いているゼミだと思います。
過去の卒論タイトル

鈴木 紀子 SUZUKI Noriko
アメリカの⽂化・アメリカ研究が専⾨分野です。特に、19世紀アメリカ⻄部フロンティアをめぐる社会⽂化的、政治的⾔説と表象に⻑年関⼼を抱いて研究を⾏ってきました。元々アメリカで⽣まれた⻄部をめぐる⾔説が、様々な媒体を通して国や時間の境界を越え異⽂化空間で再⽣されていく現象に着⽬しています。現在は、特に戦後占領期および冷戦期アメリカの対⽇⽂化政策と⽇本の受容を中⼼に研究しています。アメリカと⽇本について、学⽣のみなさんと多くの議論を重ねることを楽しみにしています。
教員から
このゼミは、アメリカの映画、文学作品、社会現象、時事問題などを取り上げながら、様々な「アメリカ」を考え、そしてアメリカを考えることで今の日本の私たち自身を考えるゼミです。特にこのゼミがテーマにしているのが、【人種・ジェンダー・アイデンティティ】です。アメリカと日本の社会文化を、この三つの視点から深く切り込みます。
ゼミでは、教員があれこれと説明を行いますが、学生のみなさんがそれぞれ独自に感じる意見を尊重したいと思っています。理想的には学生が思ったことをぶつぶつと自由につぶやけるような授業を目指しています。作品の解釈は人により幾通りもあり、その幾通りもの解釈を互いに共有し合うことが文学や文化を学ぶ上でも、また広く「人間」を知る上でも重要だと考えるからです。教員自身、学生のみなさんから学ぶところ大です。
卒業論文については、文学作品や映画に描かれたアフリカ系アメリカ人などマイノリティの人種差別問題、ジェンダーの問題をテーマに挙げる学生が多いです。それ以外の社会学的なテーマを扱うことも自由です。大学生活四年間の集大成と呼べる論文が書けるよう、できる限りサポートしていきたいと思います。
学生から
私たちのゼミでは、アメリカの映画や女性作家の文学作品、社会問題を通して、様々な問題をジェンダーと人種、アイデンティティの視点で捉え、ディスカッションします。作品を解釈するには、時代背景を考察することが不可欠です。グループ発表では、メンバーで作品について調べたり、掘り下げて話し合ったりして、様々な意見を交換して、作品を探求します。とてもやりがいがあります。鈴木先生は、優しくて、私たちがどんな意見を言っても、真剣に聞いてくださるので、とても意見が述べやすいです。卒論に関しても、親身になってくださるので、相談しやすく、アメリカの文化や文学の知識が豊富で、色々な話やアドバイスを聞けます。アメリカを語る先生は熱いです。
3年生と4年生の仲が良く、ゼミ以外でもよく話をします。食事会や合宿はとても盛り上がって楽しいです。
人種やジェンダー、アメリカの文化に興味のある方、また今まで習った授業を生かしたい方におすすめのゼミだと思います。
過去の卒論タイトル

田代 尚路 TASHIRO Naomichi
19世紀イギリスの詩が専門です。特に関心をもっているのは、ロマン派以降の詩における話者(作品内の「私」)の立ち位置です。それに関連して、詩にみられる風景描写の問題にも取り組んでいます。アルフレッド・テニスンの詩に対する思い入れが強いですが、テニスンを中心とした詩人のネットワークを作るような感覚で、ジョン・キーツ、エミリ・ブロンテ、エリザベス・バレット・ブラウニングなどにも興味関心を広げつつあります。
教員から
ゼミでは、主に19世紀の小説を読んでいます。2017年度はエミリ・ブロンテの『嵐が丘』、2018年度はジェイン・オースティンの『高慢と偏見』に取り組みました。基本的には、小説を原文で丁寧に読み、担当学生の発表を聞いてから皆で意見交換をするというかたちで毎回の授業を進めていますが、そこに英詩を専門とする担当教員ならではの味つけを加え、『嵐が丘』の際はエミリ・ブロンテの詩を、『高慢と偏見』の際にはコヴェントリ・パトモアの『家庭の天使』という詩をぶつけてみて、皆の反応を楽しみました。
2019年度はオスカー・ワイルドの小説・童話・戯曲・詩を扱っています。まず童話(「幸福の王子」など)から読み始めましたが、ワイルドにとって「愛」とは何か、「友情」とは何かなど、議論が盛り上がっています。
ゼミでは4年次に卒業論文を仕上げることになりますが、論文のテーマを決める前に、なるべくさまざまな作品に触れてもらいたいです。ゼミでの作品読解がその一助になればと願っています。
学生から
過去の卒論タイトル

千田 誠二 CHIDA Seiji
英語教育・英語学習、又は外国語・言語コミュニケーションスタイルなどを支える、個のアイデンティティや価値観を紐解いています。大妻英語英文学科生は、女子教育環境下で学ばれていることから、最近のゼミでは外国語教育・学習・コミュニケーションにおける性差(ジェンダー)の側面を扱った文献も取り入れながら、英語学習者・教育者の個の内面性を探っています。これらは、例えば英語コミュニケーションに伴う葛藤であれば、そこから遡って、普段自覚しない「内なる自身のありよう」とその「起点」を安全な環境で「確認する」作業ともいえます。中・長期的にはコミュニケーション「進行中」での個の自覚や認識の深まり、ひいては自身が望む方向への分岐点を生むきっかけとなるでしょう。国内外の学界の流れを押さえながら、必修・選択英語授業での実践や、教職課程科目で英語教育の基本技術を教える場面で、上記の知見を活かしています。
[ E-mail ]schida[at]otsuma.ac.jp
教員から
かつて自身の英語学習・教育を改善する上で、数理的な研究・分析をメインとし、短期間に多くの語彙を習得する実践などを行なっていた自分がナラティブ(語り)研究に変更した背景は、奇しくも昨今のコロナ禍がもたらした我々人間生活の変化で起きていることと大変よく似ています。大抵の病気を抑えてきた現代医療をもってしても、科学データが集まった段階でワクチン等を適用した頃には、また別の新たな変異を持つ存在が現れて私たちの生活が再び変化させられる。このサイクルの速さは医学の専門家が予想できない程のものと言います。現代社会における科学と人間の関係のあるべき姿は、20世紀では当たり前とされていた関係性とは逆の、つまり、私たち人間の「生活(行動)・思考」に「科学が実証する結果」を「いかに当てはめていく」ことだとある大学の有名な科学者が言っています。情報伝達のスピードが猛烈に速くなり、人間の個性や多様化が際限なく広がりを見せる中で、「人」が自身の「主体性」や「判断力」をより骨太のものにし、科学的知見との付き合いをどう深めていくかが問われているということです。それはベースとしての「自己理解」なくしては達成できないでしょう。英語教育・学習の場をより深みのあるものとするためには、自身の考え、あるいは情意面といった内面性を反映する自己表現が必ず伴います。外国語コミュニケーションの実践の場では、「自己理解」は最も大事なステップと言えます。そんな思いを抱きつつ、セミナーでも学生の皆さんとあれやこれや意見を出し合っていきたいと思います。
学生から
過去の卒論タイトル

夏目康子 NATSUME Yasuko
英語圏児童文学作品とイギリス小説を研究しています。『不思議の国のアリス』ひとつをとっても、ジェンダーの視点、挿絵と物語の関わり、マザーグースの歌から読み解く物語構造、動物の擬人化、日本における翻訳の歴史と翻訳比較、ビートルズの歌への影響など、いろいろな観点から分析できます。
また、日本の絵本やポップカルチャーやジブリアニメなどが世界でどのように受容されているかについても研究しています。日本の絵本やポップカルチャーの豊かさを世界に発信できたらと考えています。
[ E-mail ]y-natsume@otsuma.ac.jp
教員から
英語という言語の背後には、音楽、物語、映画など豊かな世界が広がっています。日本語とは言語体系が異なる英語という言語を学ぶことにより、日本語を見つめ直すきっかけにもなります。
ゼミでは、『不思議の国のアリス』を読み解きながら、英語の言葉遊び、パロディ、ナンセンス、挿絵の持つ意味、ジェンダー観などについて考えます。また、日系イギリス人カズオ・イシグロの『クララとお日さま』を読み、AIが台頭する近未来社会について考えます。毎回、マザーグースや英語の歌を聴いて、音声面からも英語の楽しさを味わいます。
学生から
過去の卒論タイトル

早川 友里子 HAYAKAWA Yuriko
19世紀ヴィクトリア朝小説が専門分野です。これまで主にブロンテ姉妹(シャーロット、エミリ、アン・ブロンテ)やエリザベス・ギャスケルなどの女性作家の小説における様々な女性の自伝的な語りの表象に関心を持ち、研究してきました。現在は、ヴィクトリア朝小説における女性の体や病の表象と語りとの関連に着目しています。
教員から
一つの作品に対して多様な切り口や解釈が可能であることが文学の大きな魅力の一つです。このゼミでは主に19世紀ヴィクトリア朝の小説を精読します。学生の皆さんの様々な視点や考察を大切にしながら、作品への理解を深めていくことを目指しています。皆で考えを共有しつつ読み進めていくと、新たな気づきを得ることもあるはずです。だからこそ、授業では原文とじっくりと向き合いつつ、互いの考えにも耳を澄ませる姿勢を大切にしていきたいと思います。
優れた小説との出会いは、時に新たな自分を知るきっかけにもなります。皆さんにはゼミを通して多くの作品に触れ、自分なりの特別な一冊を見つけてもらいたいと願っています。
学生から
女性作家の作品、女性を主要人物とした19世紀ヴィクトリア朝小説について学びました。物語の面白さはもちろんのこと、テクストから浮かび上がる論点を丁寧に考察していくので、小説の新たな魅力を知ることが出来ました。時代、そして国が違っても、同じ女性として深く考えさせられる内容です。授業の雰囲気は和やかで、取り扱うテーマが面白いので参加しやすいと思います。卒業論文は先生がしっかりとサポートしてくださいます。親身に指導していただき、とても相談しやすかったです。
19世紀ヴィクトリア朝時代の女性作家が書いた小説を題材に当時の女性の立場や権利について学んでいます。昨年は『ジェイン・エア』などの作品を扱い、物語を味わうだけではなく、そこから浮かび上がる問題に焦点を当て学んでいきました。その他、扱う小説は面白いものが多く楽しく学ぶことができます。また論点となる問題は決して他国の昔話ではなく、現代の日本にも深く根を張る問題です。私自身このゼミで学ぶことによって新たな考え方や視点を持つことができるようになりました。授業の雰囲気は暖かく穏やかでとても自由で参加しやすいと思います。もし不明な点があっても先生が優しく分かりやすく教えてくださるし、様々な参考文献を配布してくださるので授業内で解決することができます。
過去の卒論タイトル

村上 丘 MURAKAMI Takashi
言葉は、<タテ>と<ヨコ>の両面から見ることができます。たとえば The soup is good. という文では、the, soup, is, good という4つの語が、<ヨコ>の関係に並んでいるということができます。<ヨコ>の関係にある語は、互いにつながりあい、文全体の意味を作り出します。
一方、この文の is の位置には、他に tastes, smells, looks 等の動詞が来ることができますが、これらの3つの語は、<タテ>の関係にあるということができます。<タテ>の関係にある語は、文の中の同じ場所を占めるだけでなく、互いに共通の意味(ここでは、味覚、臭覚、視覚という人間の感覚)をもっています。
このように、言葉を<タテ>と<ヨコ>の2つの観点から眺めると、形と意味との関係が明らかになってきます。すなわち、言葉を考える時は、表面(<ヨコ>の関係)だけでなく、内面(<タテ>の関係)にも注意しなくてはなりません。
このような物の見方は、言葉だけでなく、他の場合にも当てはまります。物事を深く、緻密に考えるには、目に見える部分と、見えない部分の両方に目配りをしなくてはなりません。言葉を研究することは、世界の見方を学ぶことにつながるのです。
[ E-mail ]rosetta@otsuma.ac.jp
教員から
このゼミでは、英語学の領域で卒業論文を執筆するために必要な、知識と技法を習得することを目指します。授業では、2種類の学習支援システムを併用します。課題の提出は、manabaを通して行います。課題の発表と画像の表示は、CALLを利用します。個々の発表の直後に、全員がmanabaでコメントを入力します。卒論の素材は、新聞・映画・広告・歌詞・小説・コーパスなど、多岐に渡ります。
学生から
過去の卒論タイトル

森井 美保 MORII Miho
私の専門は現代アメリカ文学で、なかでもジョイス・キャロル・オーツの作品を中心に研究しています。オーツの小説は、一読しただけではその真意をつかみにくく、解釈が難解なものが多いと感じています。けれども私は、文学作品のメッセージを読者が必ずしも作者の意図どおりに受け取る必要はないと考えています。読者はそれぞれの経験や価値観、育った環境などをもとに、自由に作品を読み解いてよいのではないでしょうか。オーツの物語に潜む深いメッセージを探りながら、自分なりの解釈を模索する日々を送っています。
教員から
皆さんは、テレビやインターネットのニュースを見て、怒りを覚えたことはありませんか?日々の生活の中で、不条理だと感じる瞬間はありませんか?世の中に対して、何か言いたいと思うことはありませんか?こうした感情を抱いても、それをぶつける場所を見つけるのは簡単ではないかもしれません。けれど、文学や映画の研究を通じてなら、その思いを言葉にすることができます。なぜなら、私たちが日常で感じる怒りや理不尽さは、たいてい文学や映画の中ですでに描かれているからです。もし、心の中に言葉にできないモヤモヤを抱えているなら、自分のお気に入りの作品を見つけてみてください。そして、その作品を通して、自分の思いを表現してみませんか?このゼミでは、皆さんが自分の考えをしっかりと表明できるようになるためのサポートをします。「何かについてじっくり考えたい」「その考えを自分の言葉でまとめてみたい」と思う方は、ぜひ私のゼミに参加してください。
私の専門は現代アメリカ文学で、特にジョイス・キャロル・オーツの作品を研究しています。オーツは1938年生まれで、現在85歳を超えていますが、今なお精力的に執筆活動を続けている作家です。日本ではあまり知られていないかもしれませんが、毎年のようにノーベル文学賞候補に名前が挙がる実力派の作家です。このゼミでは、前期にオーツの短編小説を数編読み、それぞれについてディスカッションを行います。後期には、前期に読んだ中から一つ好きな作品を選び、それを題材に研究を深めて、最終的には一本のレポートに仕上げていただきます。これは、卒業論文を書くための予行練習と考えてください。自分の主張を明確にすること、その主張を支えるために文献を調べ、適切に引用することなど、論文作成に必要なスキルを、この後期の時間を通じて実践的に学んでいただきます。
過去の卒論タイトル
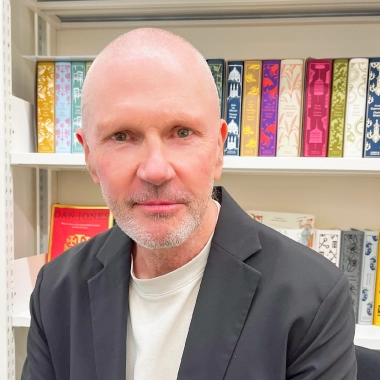
ハウエル・エヴァンズ Hywel EVANS
言語と認知の関係に強い関心を持ち、言語を「人と人が思考を共有するための道具=協調的思考のインターフェース」として捉えています。授業では、学生一人ひとりが自身の関心や問いを起点に学びを深められるよう、対話を重視しながら柔軟に伴走しています。言語そのものだけでなく、「言語はどのように学ばれるか」にも関心があり、AIの教育応用や思考支援ツールとしての可能性を探っています。卒業論文では、言語や文化に広く関わるテーマを歓迎しています。
[ E-mail ]hywel@otsuma.ac.jp
教員から
このゼミでは、学生一人ひとりが自分の興味に基づいて主体的にテーマを選び、深く探究することを大切にしています。特にAIが加速度的に進化する現代においては、高度な情報検索や分析が可能となり、従来では考えられなかったような深みと独自性を持つ卒業論文が実現可能です。こうした時代だからこそ、既存の枠にとらわれず、自らの問いと熱意を出発点にする姿勢がますます重要になります。そのチャンスを活かさないのは、あまりにもったいないことです。
学生から
過去の卒論タイトル
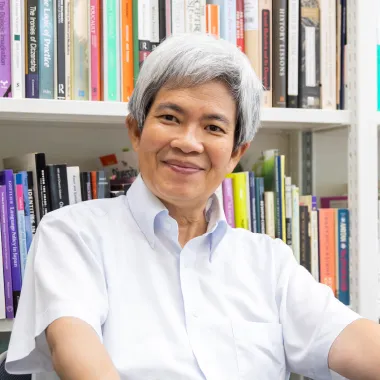
ケン・イケダ Ken IKEDA
I am an American-born Japanese from Los Angeles, California. I am interested in English education (English language identities) and Asian American culture (history and media representation).
I want to give students many ways and opportunities to discover relationships between their study, their interests and their lives. It is my hope to help students build communication and critical thinking skills, so that they can become mature and ready for Japanese society and the global community.
[ E-mail ]ikedak@otsuma.ac.jp
教員から
このゼミでは、学生一人ひとりが自分の興味に基づいて主体的にテーマを選び、深く探究することを大切にしています。特にAIが加速度的に進化する現代においては、高度な情報検索や分析が可能となり、従来では考えられなかったような深みと独自性を持つ卒業論文が実現可能です。こうした時代だからこそ、既存の枠にとらわれず、自らの問いと熱意を出発点にする姿勢がますます重要になります。そのチャンスを活かさないのは、あまりにもったいないことです。
学生から
このゼミでは、アジア人かアメリカ人の歴史と文化について学びます。アメリカへ移民した頃の背景、その後の生活体験、アイデンティティーの葛藤などを根本から探究します。
言葉や外見だけで人を判断する恐ろしさを学びました。 授業はDVDやエッセイなどを使い、アジアン系アメリカンの人々が話す言葉にも触れます。夏には合宿にでかけたりと、広がりもあり、和やかでとても楽しいゼミです。
授業は英語で行われます。特に英語を積極的に使いたい人におすすめです。
過去の卒論タイトル

