李 美淑
専門分野
メディア研究、ジャーナリズム研究
オフィスアワー
火曜昼休み E866B
榎本 恵子
専門分野
演劇論、フランス文学・文化
オフィスアワー
前期火曜昼休み 後期木曜昼休み E864B
興津 妙子
専門分野
国際教育開発論、比較教育学
オフィスアワー
火曜昼休み E867A
川村 覚文
専門分野
メディア文化論、カルチュラル・スタディーズ、批判理論
オフィスアワー
火曜昼休み E869A
上村 博昭
専門分野
経済地理学、地域公共政策
オフィスアワー
月曜昼休み E867B
関本 紀子
専門分野
東南アジア地域研究、ベトナム社会経済史
オフィスアワー
月曜2限 E864A
竹部 成崇
専門分野
社会心理学
オフィスアワー
国外研修中
戸田山 祐
専門分野
アメリカ史、国際移民研究
オフィスアワー
月曜昼休み E869B
松田 春香
専門分野
東アジア国際関係史、韓国・朝鮮近現代史
オフィスアワー
月曜昼休み E868B
松村 茂樹
専門分野
アジア太平洋国際交流論、サーバントリーダーシップ論
オフィスアワー
前期月曜昼休み E868A
守田 美子
専門分野
英語学、英語教育
オフィスアワー
月曜昼休み E865B
横濱 雄二
専門分野
映像文化論、日本文化論
オフィスアワー
火曜昼休み E865A
吉田 光浩
専門分野
日本語学
オフィスアワー
火曜昼休み E863B

李 美淑 Lee Misook
他者との「境界」がどのように(再)構築、強化されるのか、また、一方で、どのように「境界」を越え、他者との「連帯」が志向されるのか、をメディア、ジャーナリズム研究および歴史社会学的なアプローチで考察しています。女性や社会的弱者に対するメディア言説とジャーナリズム、国境を越える社会運動とメディア実践、ジャーナリズムの国際比較研究を行っています。
教員から
メディアとジャーナリズムを通して、社会のあり方を批判的に読み解きます。ゼミの皆さんには社会の様々なイシューに関心を持ち、それらがメディアとジャーナリズムでどのように語られているのか、あるいは語られてもいないのか、また、社会的にどのように認識されているのか、など普段から考えていってほしいです。
現在のメディアとジャーナリズムは、それらがおかれているグローバルな政治経済文化的な文脈やデジタル技術とともに考察していく必要もあります。みなさんが普段使っているソーシャルメディアを含め、メディアとジャーナリズムにかかわるグローバルな現象、またはデジタル技術とともに現れる特性にも関心をもってほしいと思います。

榎本 恵子 ENOMOTO Keiko
私がフランス語を学ぶきっかけの一つは『ベルサイユのばら』でしたが、専門はその舞台となったヴェルサイユ宮殿を建てたルイ14世の時代―17世紀の喜劇です。中学で演じたモリエールの『守銭奴』、大学の恩師の授業で読んだ『ドン・ジュアン』との出会いが私の専門の方向性を決めました。17世紀の教育論、翻訳論、演劇論、劇作法を扱っていますが、18世紀、19世紀の演劇へと対象を広げています。
高3から続いているフランス人のペンフレンドは、自分が日本語を勉強するより、私の方がフランス語を長く勉強するだろうと思っていたそうですが、事実、大妻コミ文で皆さんと共にフランス語、文化、文学ワールドを繰り広げることになりました。
教員から
このゼミはフランスに興味のある学生が集うゼミです。パリやフランス各地の城や街の景観・建築に興味がある学生、バロック、ロココの絵画に興味がある学生、映画や戯曲に興味がある学生、ドレスや60年代の服装、食文化、教育、文学などいろいろな分野に興味がある学生が集まっています。
最初からテーマが決まっている学生、たくさんありすぎて悩んでいる学生それぞれです。各々が自分の興味の対象を学習し、みんなで話しあったり、共通の課題を学習することで視野を広げていきます。
日本におけるフランスは今どんどん増えてきています。2018年には日仏交流160周年を迎えました。フランス語が公式第一言語であるオリンピック・パラリンピックが2021年東京で開催、2024年にはパリと続きました。また2024年に新一万円札の肖像画として選ばれた渋沢栄一に焦点が集められ、巷ではフランスへの関心が高まっています。ゼミでは、この、私たちの周りにあふれるフランスを、フランス大使館や総務省見学、テーブルマナーなどの学びを通して理解を深めていきます。そして私たちの身近にあふれているフランスを感じながら、資料収集、文献表の書き方、発表・レポートの構成・書き方を学び、卒論へと結び付けていきます。
学生から
私たちのゼミでは、穏やかな雰囲気の中で、毎週有意義な時間を過ごしています。
学生たちは、フランスのみならず文化や芸術を、それぞれ違った視点や考えから探究しています。異なるテーマではありますが、どこかで共通点を見つけた時はとても楽しいですし、「フランス」を内面的に見るか外面的に見るかで面白さも変わります。
榎本先生は学生一人一人に細かいサポートをしてくださり、ゼミの時間以外でもとても充実した日々を送れます。

興津 妙子 OKITSU Taeko
これまで長年にわたり、外務省、国際協力機構(JICA)、国連児童基金(UNICEF)カンボジア事務所等で国際協力の実務に携わってきました。現在は、アフリカのザンビア共和国を主なフィールドとして、教育開発や国際教育協力のあり方について研究を進めています。研究においては、教育のあり方は、それぞれの社会の文化、価値観、歴史を踏まえてその社会に暮らす人びと自身が決定すべきであるという視点を大切にしています。
2015年9月に世界のリーダーたちは「持続可能な開発目標(SDGs)」を採択しました。これは、世界から貧困を終わらせ、将来の世代のため地球環境も守りながらすべての人が豊かな生活を送ることができる世界を目指す国際目標です。SDGsの第4目標では、すべての人が質の高い良い教育を受けられることを目標としています。しかし、これまでの「開発」や教育のあり方が今の持続不可能性を生み出しているのであれば、私たちは豊かさの定義を問い直し、過去を反省的に見つめ直すことも必要です。そして、「発展途上国」というラベルで語られてきた国や社会の多様な知のあり方からも学ぶという視点が求められています。自分たちの「当たり前」を疑い、地球規模課題解決のため、多様な文化を生きる人びととの対話をどう進めていくべきか、学生の皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。
[ E-mail ]t.okitsu@otsuma.ac.jp
教員から
このゼミは、貧困、格差、紛争、飢餓と飽食、環境破壊などのさまざまなグローバル課題と国際協力に関心のある学生が集うゼミです。近年は、日本における多文化共生やジェンダー不平等について研究する学生も増えています。
学生たちは、世界の様々な課題について、日本に暮らす自分たちとの関係も踏まえながら深く考え、解決策を検討します。各自がそれぞれの経験を持ちより、様々な角度から議論することで、思いがけない気づきが見えてきます。政府援助機関やNGOなどの援助機関などを訪問し、生きた国際協力を学ぶ機会も大切にしています。
私自身、ゼミ生から学ばせてもらうことも多く、教員―学生という立場を超えた学びのサークルを目指しています。
学生から
私たちのゼミでは、主に「国際協力」を研究対象としています。今日、日本や世界で問題となっている飢餓や貧困、ジェンダー平等に関する課題や難民・外国人労働者の受入などの問題に興味のある学生が多く、先生は現代の様々な問題に詳しく、学生一人ひとりの研究テーマについて、親身に相談にのってくれます。ゼミ生もとても仲が良く、授業では学生だけで意見を出し合い、他の人の考えも参考にしながら、研究に取り組んでいます。

川村 覚文 KAWAMURA Satofumi
オーストラリアの大学での博士研究以来、私の一貫した問題関心は、文化と技術の政治性についてです。文化を通じて、私たちは様々な抑圧に抵抗することが可能になる一方で、特定の考えや規範などを押し付ける抑圧的なものとしても、文化は機能します。そして文化は、そもそも文字や絵を書いたり、何かの媒体に記録したりといったような技術がないと成り立ちません。このような視座のもと、現代のメディア文化について考察しています。
[ E-mail ]satofumi.kawamura[atmark]otsuma.ac.jp
教員から
このゼミでは、現代社会の可能性と問題について、主にテクノロジーとメディア文化という観点から、学んでいきます。この社会を支える高度なテクノロジーは、多様な人々がお互いにコミュニケーションすることを可能にし、個人では達成できないような「集合的知性」の構築を可能にしてくれる一方で、諸個人を情報の束に還元し、「管理」あるいは「監視」する対象へと引き下げることも可能にしてしまいます。こういった可能性と問題の背景にあるテクノロジーがどのような原理によって駆動しているのか、そして、その可能性と問題がどのようにメディア文化やポピュラー文化に反映されているのか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

関本 紀子 SEKIMOTO Noriko
東南アジア地域研究、特に植民地期ベトナムの社会経済史を専門としています。長さや重さを量る際の計量器や計量単位といった度量衡を主に研究してきましたが、鉄道や水運などの交通運輸史や、ヒト・モノの移動・流通についても関心を持っています。ベトナムの北・中・南部の地域性を、計量器・単位や交通・流通網などの具体的な事象から解明していくことも、主要な研究課題の一つです。
教員から
東南アジアは、地理・地形や気候条件から民族、言語、宗教に至るまで、多様性に富んだ地域です。また、古くから世界のあらゆる地域ともつながりを持ち、多くの文化や文明の影響を受け、独自の発展を遂げてきました。
このゼミは、そんな豊かな東南アジア世界に興味・関心を持つ学生に向けて開かれています。それぞれが魅力を感じるテーマを軸に、歴史的・文化的観点から広く、そして深く掘り下げ、卒業研究を進めていきます。
ゼミを通じて、教員学生共に多面的で幅広い視野を養い、私たちとは背景の異なる社会や文化、事柄や人々に対しても、豊かな想像力をもって理解することができるよう切磋琢磨していきたいと思います。
過去の卒論タイトル

竹部 成崇 TAKEBE Masataka
専門は社会心理学です。社会問題の背後にある心の働きを解明して、より良い社会を目指す際に有用な知見を提供できればと思っています。現在は特に、なぜ集団はときに分裂し、争い合うのかについて研究しています。最近は、発達障害に関する事業への寄付を促進する方法についても研究したいと思っています。
より詳細な情報についてはこちらをご覧ください。
教員から
このゼミでは、人の心と行動について、実験あるいは調査を通じて研究します。具体的にはまず、自分の興味に関連する学術論文を読み、それを踏まえて自分自身の問いを立てます。次に、その問いに対する仮説を立て、その仮説を検証するための実験あるいは調査を実施します。そして、得られた数量的なデータに対して統計的な分析を行い、考察をします。数量的なデータの分析方法を学ぶのは大変かもしれませんが、自分の仮説に対する客観的な答えを得られるのはとても面白いと思います。その面白さを感じてもらえればうれしいです。
学生から
私たちのゼミでは、社会現象や人々の行動の背後にある心の働きについて研究します。論理的に仮説を立てたり、仮説を検証するための調査や実験を設計したり、統計を使ってデータを分析したりするのは、正直かなり大変ですし、やることも結構多いです。ただ、大変なだけに、データを分析するときはワクワクします。また、作業をする中でグループのメンバーとの仲が自然と深まります。仮説と全然違う結果になるとちょっと残念ですし、どうしてそうなったのかを考えたり、それを踏まえてきちんとした研究報告資料を作ったりするのは大変ですが、そこで身に付く分析的な考え方や論理的な表現方法は、ゼミ以外のところでも役立っています。
過去の卒論タイトル
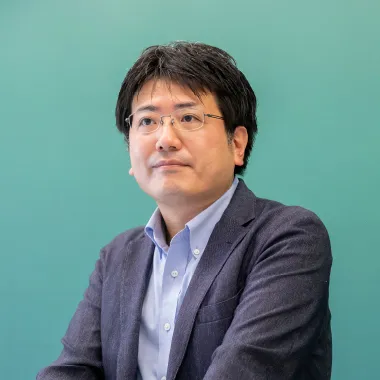
戸田山 祐 TODAYAMA Tasuku
私の専門はアメリカ合衆国とメキシコの歴史です。とくに、両国のあいだを移動する移民や、メキシコ系アメリカ人の歴史を研究しています。また、最近では移民政策をめぐる合衆国内の政治の歴史的展開と現状にも関心があります。いま、この世界で起きていることの経緯と背景を、歴史学の手法をもちいて読み解き、明らかにしようというのが、私の研究の基本的なスタンスとなります。
[ E-mail ]todayama【アットマーク】otsuma.ac.jp
教員から
このゼミでは「アメリカ史/アメリカ地域研究」と「移民研究」について学びます。アメリカ合衆国だけではなく、カナダ、カリブ海諸島、ラテンアメリカといった、南北アメリカのさまざまな国や地域の歴史・政治・経済・文化に関心がある方も大歓迎です。「移民研究」では、アメリカに限らず、日本を含めた世界各地で、国境を越えて移動する人々の歴史と現状を考えます。
本ゼミでは、文献の講読と各自の研究テーマの報告を通じて、皆さんがみずからの意見を伝え、他者の考えを理解する能力を高めることを目指します。世界でいま起きていることについて、その背景を含めてもっと知りたいという熱意を持った方、このゼミでともに勉強しませんか。
過去の卒論タイトル

松田 春香 MATSUDA Haruka
近現代の朝鮮半島を中心とする東アジア国際関係史を主に研究しています。米国・韓国などの外交・軍事文書を収集し、それらを読み解く作業は骨が折れますが、自ら「現地」に出向き、見聞を広げることは何にも代えがたい喜びでもあります。
[ E-mail ]haruka.matsuda[at]otsuma.ac.jp
教員から
このゼミは、「国際関係学」や「東アジア研究」に関心を持つ学生に開かれています。「国際関係学」を研究する学生は、戦争・紛争・難民など、日本や世界で起きている問題を取り組んでいます。また、「東アジア研究」では、韓国・北朝鮮を中心とする東アジア諸国の政治・経済・社会・文化を広く学び、日本が今後それらの国々とどのように付き合っていくべきかを考えています。
本学科もそうですが、現代世界の様々な問題を広く研究できるのが、このゼミの大きな特徴です。ゼミの集中講義では、多国籍タウン・新大久保でフィールドワークを行い、「多文化共生」の現状と課題を考えました。
学生から
本ゼミには、朝鮮半島研究や国際関係に関心のある学生が集まっています。私は卒業論文で北朝鮮の難民について取り上げるので、朝鮮半島のことも国際関係のことも学ぶことが出来るこのゼミに入って後悔をしたことはありません。なんといっても一番の魅力は、国際交流に関心が高い仲間と共に学べることです。3年次のゼミ合宿で行った外国人留学生との交流会では、外国人にとって日本はどのようにうつっているのか改めて考えるきっかけになり、とても良い経験になりました。
過去の卒論タイトル

松村 茂樹 MATSUMURA Shigeki
私は、中国の文化人の研究をしており、博士論文のテーマは、「中国最後の文人」といわれる呉昌碩でした。ところが、2015年度、ボストン大学客員研究員として米国ボストンに滞在し、米国の「個」が「ヨコ」に繋がる「ヨコ社会」に興味をもったのです。そして、日本の「タテ社会」を「ヨコ社会」に変革すべく、米国発の「サーバントリーダーシップ(servant leadership:リーダーとして「ヨコ」のつながりを重視し、他者へ仕える精神)」の研究へ新たに取り組んでいます。研究は、興味が大切です。みなさんも自身の興味を大切にして研究に取り組んでください。私も「サーバントリーダーシップ」の精神で、みなさんをサポートしたいと思っています。
[ E-mail ]shigeki.matsumura[at]otsuma.ac.jp
教員から
ゼミは大学の醍醐味を堪能できる場です。ゼミ生一人一人が興味あるテーマに取り組み、教員がそれを研究として成り立つようサポートします。そうして卒論を書き上げた時、みな充実感を得ます。それは、自説を説得力ある形で、論文にまとめあげ、思考し、発信できる人になれた喜びからです。
また、ゼミでは、かけがえのない仲間を得ることができます。学問の場を共にする仲間と、2年間を濃密に過ごすことで、みな確実に豊かな人になって行きます。毎年、ゼミ生を社会に送り出しながら、それを実感しています。
学生から
私たちのゼミは、とても仲が良くアットホームなゼミです。そのため、授業内でのディスカッションでも学年・クラスの垣根を越え、意見を言いやすい雰囲気になっています。ゼミ合宿や企業訪問など、学校外での活動が多いところも魅力の1つです。また、卒論や進路のことなどで相談があれば先生が親身に聞いてくださいます。ゼミ生の間では「困ったことがあれば松村先生へ」が合言葉。このゼミに入り、最高の仲間・先生に出会えてとても幸せに思います。
2023年度松村ゼミ卒論題目

守田 美子 MORITA Yoshiko
専門は言語学と英語教育です。このゼミでは、日本語と英語を比較することで浮かび上がる共通性や相違点を考え、これがコミュニケーションの場でどのように作用するか、また英語教育の現場でどのように生かしていくべきかについて考察することができたらと考えています。またグローバル化の時代の中で、日本人の英語によるコミュニケーションがどうあるべきかについても関心を持っています。
教員から
このゼミでは、ことばについて誰もが抱くような日常の疑問について、深く掘り下げていけたらと考えています。ちょっとした日本語と英語の違いが、同じものを見ても異なる視点から表現する言語観の違いから発生していることもあれば、時には社会や文化の違いと関連していることもあります。また、日本語と英語の全く異なってみえることばの現象が、実は非常に類似した現象に還元できることもあります。授業を通して学生さんたちが、言語の違い、コミュニケーションの違いを認識した上で、複眼的に物事をとらえることができるようになってもらいたいと考えています。
学生から
わたしたちのゼミでは、日本語と英語による表現の違いや、それに伴うコミュニケーション・スタイルの違いを、映画などの分析を通して学んだり、また英語教育の観点から考察したりして学んでいます。同時に学修したことについて、自分の意見を論理的に発表したり文にまとめたりするスキルもより向上できるよう努力しています。みんなで助け合いながら全員が卒業研究を完成させられるよう、先生と一緒にがんばっています。
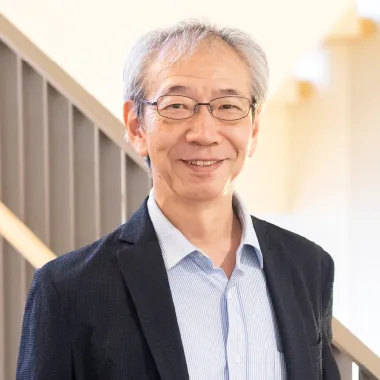
吉田 光浩 YOSHIDA Mitsuhiro
日本語の語彙論・日本語史が専攻分野です。ひとつひとつの言葉がどのように生み出され、普及し、消えてゆくのか、また、日本語がどのようにして現在のような姿になったのかという問題について興味を持っています。最近では、言葉が、さまざまな非言語の要素とどのように関係しながらコミュニケーションを成り立たせているのかという問題についても関心を持っています。
教員から
「研究」「卒業論文」というと日常生活からかけ離れた難しいことに取り組むものというイメージを抱いている方も多いと思いますが、決してそうではありません。例えば私のゼミでは、日本語または日本語コミュニケーションについて取り組む学生が多いのですが、そこで扱う内容は日本語ですので、表面的に理解することはさほど難しいことではありません。しかし、そのデータの裏には、思いもよらない面白い発見が隠されていることがあります。また、コミ文では、幅広い分野をカバーするように学科の内容が設定されていますので、日本語以外のテーマに取り組みたい学生も歓迎しています。一緒にゼミに参加してみませんか。
学生から
吉田先生のゼミには、主に「ことば」や日本語によるコミュニケーションに関心のある学生が多いのですが、ひとりひとりのテーマはとても幅が広く、日常会話やマンガ・ドラマ・ラジオ放送・映画、古典文学など自分の興味があるメデイアからデータを収集して、それぞれ研究を進めています。落ち着いたアットホームな雰囲気の中で楽しみながら自分のテーマに取り組める環境があります。卒業論文というと自分に書けるのだろうかと最初は不安に思うかもしれませんが、具体的な書き方を基礎から丁寧に教えていただけるので、安心して研究に取り組むことができます。
過去の卒論タイトル
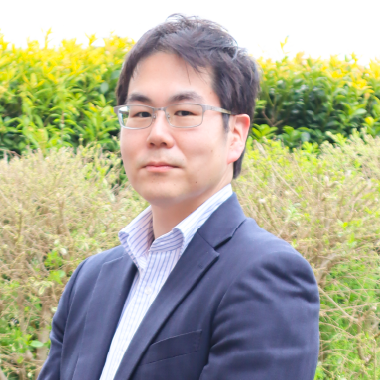
上村 博昭 KAMMURA Hiroaki
地域の特徴を経済的な視点から検討する経済地理学を専門としています。大都市圏の経済活動、特に流通業・商業の動きにも関心を持っていますが、これまでに研究の中心となっていたのは、地方中小都市や農山村、離島の経済地理的な分析です。人口減少や産業の衰退という課題がみられる地域で、どのように産業を維持・発展させるのか、特に、食を活かした地域振興の在り方について、当事者の方々の動きや政策的対応に着目しながら研究をしてきました。データ分析や文献での検討に加えて、現場での学びを大切にしながら、地域の諸課題とその解決策の検討を進めたいと考えます。
教員から
私の専門である地理学について学びます。地理学と聞くと、地名や統計を暗記するイメージがあるのかもしれませんが、ゼミでは、地域にみられる諸課題に注目して、なぜそのような課題が生じるのか、どのように解決や改善をできそうか、という視点で考えます。たとえば、人口減少や高齢化が進む地域で、域内の資源を活用して何をできるのか、主体やその関係、政策的な枠組みなどをふまえて考察する、という観点です。テキストで語られる「理論」や「成功例」に捉われず、現場で見る・聞く・確認することを経験しながら、地域の諸課題や解決に向けた動きを分析・考察して、地域の実情への理解を深めていきます。

横濱 雄二 YOKOHAMA Yuji
日本映画、アニメーション作品、文学作品のテクスト分析を専門としています。たとえばテクストと実在の地理や歴史的事象と対照し、両者の差異から、テクスト固有の意味を考えます。また複数の媒体(映像、図像、文字、音声)で展開するメディアミックス作品をとりあげ、各媒体の差異や共通項に着目して分析することもあります。これらによって、多様なメディアで展開されるテクストのあり方を探っています。
[E-mail]yokohama[atmark]otsuma.ac.jp
教員から
ゼミでは、日本の表象文化、つまりさまざまなメディアで展開される物語について、それらをめぐる文化的事象を含め、広く考察の対象とします。具体的には、実写映画やアニメーションはもちろん、マンガや小説などの作品、さらには作品と関係する地域の地理や歴史なども含みます。
わたしたちは、日々新しい作品や表現に触れており、その意味でつねに最先端の表象文化を生きています。しかし、それらに触れるわたしたちが、ものの見方や考え方を日々更新し続けているわけではありません。ゼミでは、映画学や文学などの物語を対象とする理論、概念、分析方法、歴史を学び、作品を多角的に捉える力を養います。それは、わたしたちが生きている現在の社会、さらにはこれからの社会を捉えることにつながるでしょう。
みなさんはそれぞれ異なるものの見方をして、異なる知識を持っています。お互いが教え合い、学びあうことで、多角的に捉える力はさらに強くなります。ぜひ、みなさんがそれぞれの意見を出しあって、ともに学ぶことを目指しましょう。

